“これ”を知らずに歯科治療をして大丈夫ですか?
全身疾患を持つ患者さんの歯科医療に際しては、訪問診療の臨床で使える全身疾患や薬剤の知識が不可欠です。
ですが、教科書では基礎的な知識しか学べず、実践的な知識を学べる機会は滅多にありません。
そこで、内科医と歯科医のダブルライセンスを持つ日本大学 歯学部の米永先生に、訪問診療の臨床で役立つ全身疾患の知識を解説していただきました。
ここでは、その一部をご紹介します。
糖尿病患者の注意点
糖尿病患者の観血的処置の際に気を付けたいのが、治療時の血糖値とHbA1c。コントロール状況が良くても、炎症があると血糖値の変動が大きくなるためです。
このため、治療前にデキスターなどで血糖値を測定して異常がないことを確認することが推奨されます。また、空腹時血糖値を20で割った値がHbA1cとほぼ同じと言われており、それに30を足すと重症度がわかります。
例えば、血糖値が160の場合、HbA1cは8%と推定され、それに30を足すと38です。それを体温に見立てると38℃ですから、合併症の危険が高くなっていると判断できます。
脳血管疾患患者で確認すべきこと
一般的に、脳梗塞患者には抗凝固薬としてDOACが処方されますが、ワーファリンを服用していたら、服薬アドヒアランスが悪く、コントロール不良かもしれないと考えて注意が必要です。
DOACの半減期が24時間なのに対して、ワーファリンの半減期が1週間ほどなので、服薬アドヒアランスが悪い患者はワーファリンが処方されることが多いためです。
もし、目の前で患者の顔面の歪みがある、上肢の脱力がある、ろれつが回らないという症状があれば脳梗塞発症の疑いがあるため、速やかに脳卒中センターに移送する必要があります。
喘息患者の歯科治療のポイント
喘息患者の歯科治療前に確認すべきことは、喘息発作の既往があるかどうかです。喘息と喘息発作は別物と考えた方が良いです。喘息発作が起こると、それに伴って呼吸困難になることもあり、生きるか死ぬかといったところになってくるためです。
喘息発作から約1年から2年経っていないと落ち着いた状態とは言えません。半年後だとまた急に起こるかもしれないという心構えと準備が必要です。
喘息発作時には、吸入ステロイド薬(ICS)などの長期管理薬は効果がありません。患者が増悪治療用のβ刺激薬(SABA)を持っていることを確認する必要があります。
なお、喘息患者の約10%がアスピリン喘息なので、ロキソニンは出さない方が安全です。アスピリン喘息が起こってしまったらリン酸エステルを使うのが基本です。
ここでご紹介したものは、ほんの一部です。 その他にも、高血圧、心疾患、COPD、腎不全など、訪問診療患者に多い疾患の歯科治療に際して、知っておくべきことがたくさんあります。 この機会に、安全な歯科治療実施に役立つ実践的な全身疾患の知識を身に付けることをお勧めします。
このDVDを観ることで得られることは…
- 安全な歯科診療に役立つ実践的な全身疾患の知識が身につきます
- 緊急事態を起こさせない事前の確認ポイントと、万一の対処法
- 歯科医師も知っておくべき最新の全身疾患に関するガイドラインとその要点がわかります
- 訪問診療患者に多い疾患の管理方法と薬剤のポイント
- 4つの臨床動画をもとに、訪問時の確認内容や指導方法などを学べます
などとなっています。
このDVDの収録内容をご紹介すると…
Part1:講義
1. 尿病患者の歯科診療(血糖管理と歯周病、低血糖発作の対応)
- 糖尿病概要
- 歯科での糖尿病患者の対応
- 糖尿病のイメージ
- 意識障害
- 健康食スタートブック
- おいしい健康 – 管理栄養士監修のレシピ・献立アプリ
- 登録歯科医制度
2. 高血圧・心疾患を持つ患者の注意点(降圧薬の影響、訪問先での抜歯時のリスク管理)
- 高血圧管理・治療ガイドライン2025
- 高血圧のイメージ
- 血圧を下げる10のヒント
- 歯科での高血圧症患者の対応
- 心不全概要
- 駆出率による心不全分類(2025年改訂版心不全診療ガイドライン)
- 歯科での心疾患患者の対応
3. 脳血管障害(脳梗塞・脳出血)後の患者の対応(嚥下障害、服薬管理)
- 脳血管障害
- 脳卒中・循環器病対策基本法
- 歯科での脳梗塞患者の対応
- 我が国における脳梗塞利用薬の変遷
- どれが出血でしょうか
- 嚥下障害の脳疾患の鑑別
4. 呼吸器疾患(COPD、喘息)のある患者の注意点
- 喘息予防・管理ガイドライン2024
- 喘息の病態と治療
- 喘息診療実践ガイドライン2024
- 喘息の疫学
- 歯科での喘息患者の対応
- アスピリン喘息
- COPD診断と治療のためのガイドライン2022
- 高齢者の喘息、またはCOPDをみたらACOを疑う
- 『食べる』には咀嚼、姿勢、呼吸状態が強く関係する
5. 透析患者・腎不全患者への対応(禁忌薬、感染リスク管理)
- 慢性腎臓病(CKD)
- 透析導入患者の原疾患の推移
- 歯科での腎不全患者の対応
- 腎機能低下時の主な薬剤投与量一覧
6. フレイル・サルコペニアと歯科診療の関係
- フレイルとは
- オーラルフレイルの概念図およびOF-5
- メタボリックシンドローム・サルコペニア・ロコモティブシンドローム・フレイル・イートロスの関係図
- 老年症候群
- 高齢者総合機能評価
- 体重減少の鑑別疾患
- ミールラウンドとは?
- NST(Nutrition Support Team)とは?
- 急性期におけるリハビリテーション、栄養管理及び口腔管理の取組の推進
- 【事例】リハビリテーション・口腔・栄養の連携(経口摂取への移行・在宅)
- まとめ(振返りのポイント)
- 復習テスト
Part2:潜入動画編
1. 糖尿病患者の血糖値確認と対応を学ぶ場面
- 今回の患者
- 今回の患者に対して
- 高齢者診療の魅力
2. 高血圧患者のバイタル管理と処置前の注意点
- 次の患者
- 高血圧に対する治療の仕方等
- 高血圧の影響
- フロセミドからアドセミドに切り替え
- 理想論を追うのではなく、現状でできるベストを探すことが重要
- 低血圧のリスク
- 患者ごとに臨機応変に対応することが重要
- 血管が老いると…
- 血管を老いさせないためには
- 血圧管理のポイント
3. 脳卒中後遺症のある患者の口腔ケア・食事指導
- 今回の患者
- 肝硬変患者
- 肝機能低下時は食事に注意が必要
- 栄養指導・食事支援のポイント
- 患者観察のポイント
- 身体観察の意味
- 利尿薬の影響
- 嚥下評価のポイント
- 嚥下内視鏡検査の理由
- 嚥下内視鏡検査のポイント
- 嚥下内視鏡検査での注意
- 嚥下内視鏡前の確認
- 検査のポイント
- 嚥下内視鏡のポイント
- 鼻の通りを確認
- 右鼻から挿入する理由
- 検査前の機器確認
- カメラ操作のポイント
- 声帯チェック
- スプーンの量とすくい方
- スプーンのサイズ
- 固形物の嚥下確認
- 嚥下チェックの詳細
- 内視鏡でのチェック(場合により)
- 検査終了時のケア
- 観察のポイント
- 鼻の観察
- 内視鏡の片付け
- 診察のポイント
- 肝硬変患者の注意点
- 肝硬変患者の食事の課題
- 肝硬変患者の栄養
- 肝硬変患者の栄養管理
4. 呼吸器疾患のある患者の治療方法
- 次の患者
- COPD患者の食事
- 鼻と呼吸器の関係
- 患者の呼吸苦
- 鼻呼吸の重要性
- 鼻呼吸と免疫
- 摂食改善の対応
- COPD対応の効果
- 吸入薬の効果
- COPD患者の摂食対応
- 食事中の呼吸管理
- 酸素投与の注意
- 鼻カニューラでの酸素投与
- 聴診器の活用
- ベッド・マットの重要性
- 今後もCOPD患者は増加傾向
- COPDの診断状況
- COPDと超高齢社会
- COPDと喘息は併発しやすい
- 高齢者で発症する喘息も多い
- 喘息・COPDいずれも呼吸困難により食べられないことがある
- Ambu aScopeTM 4 ライノラリンゴ
- 脂肪肝からくる肝機能障害に注意 MAFLDが注目されている
- 保険収載されている主な栄養剤
- 鼻呼吸のすすめ
- エコーによる嚥下評価方法
- エコーによる誤嚥性肺炎の評価
- 機種によるエコー画像の比較
- 食道・気管
- まとめ(振返りのポイント)
- 復習テスト
などなど。
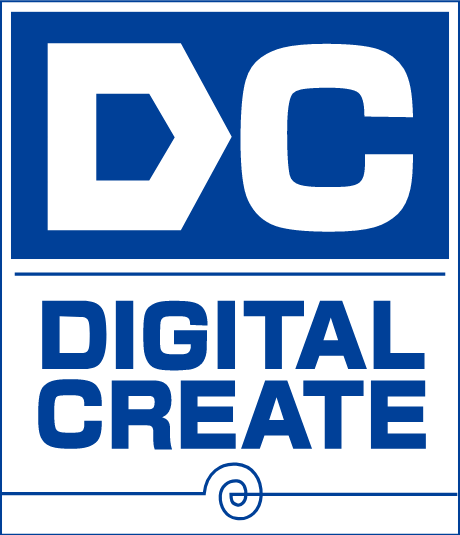
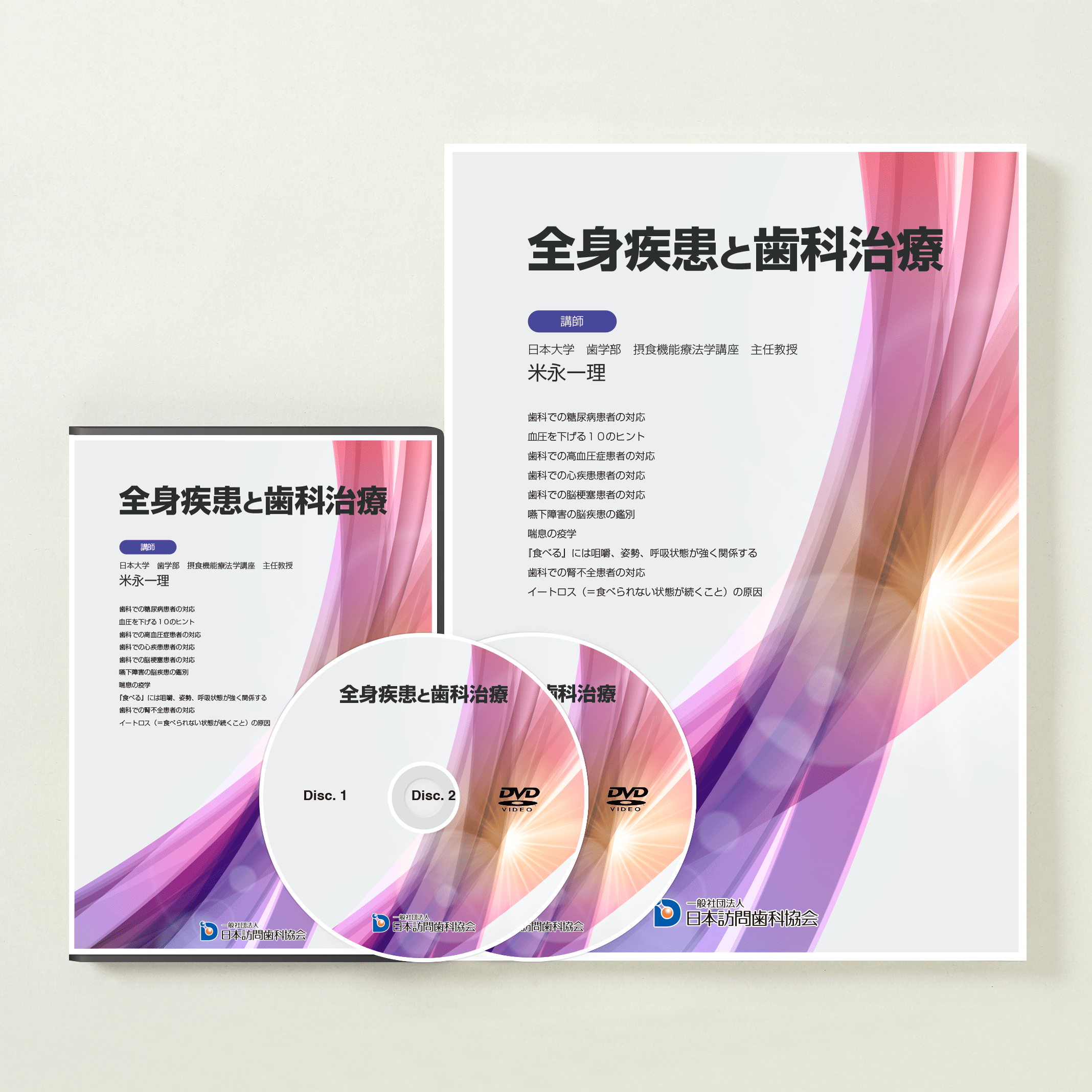
R.M. –
高齢者に多い全身疾患についての最新の情報と実際のベッドサイドなどの映像参考になりました。鼻呼吸が大切と子供から大人まで言われる今日、免疫面からの理論づけに役立ちそうです。超音波検査の将来像も垣間見られ、読影力の必要性を感じました
S.I. –
医科レベルの話が為になりました。直ぐに使わせて頂いたのは血糖値HbA1Cの数値に30を足して体温に見立てて判断する方法です
K.Y. –
訪問診療の対象患者はほとんどが多くの疾患をいくつも持ち合わせております。その疾患の背景を理解しながら歯科治療を進めることが、歯科治療の成功への鍵であるとつくづく思いました。歯科治療に関連する全身疾患についてさらに多く学ばなければならないと知らされました。大変有意義な講座であったと感謝申し上げます
K.Y. –
血圧を下げる十のヒント、イートロスの関係図参考になりました
T.O. –
患者さまの「食べる」をマネジメントする、という歯科医師の役割について、深く学ぶことができました。医科からの視点を通じて、歯科の果たす役割の重要性を再認識することができました