摂食嚥下障害患者の問診 “確認忘れ”はありませんか?
摂食嚥下診療における問診で確認することには、大きく分けると次の9項目がありますが、あまりにも確認することが多いため、確認漏れが発生することがよくあります。
主訴については、具体的にどのような自覚症状があるかは忘れることはありませんが、家族や介護職員などから他覚症状も合わせて確認する必要があります。

家族や介護職員は重大な他覚症状については覚えていますが、ちょっとした症状は、かなり深掘りして聞いていかないと出てこないことがあります。
そのちょっとした症状が、患者の症状を診断するのに役立つことが多々あります。
問診の際には、「他に気付いたことはありませんか?例えば、〇〇している時とかに。」のように、生活の中のシーンで聞いていくと良いかもしれません。
また、患者の自覚症状、介護者の他覚症状のタイミングを確認するのも大切です。熱発した後とか薬を変更した後、食事中にむせるとかいうことを確認します。
血液データ確認のポイント
直近の血液検査データがあれば、その数値を確認する必要があります。摂食嚥下障害患者は低栄養であることが多いためです。
低栄養の場合には、摂食嚥下リハビリを行うことで栄養状態を悪化させてしまう恐れがあります。
栄養状態の指標となる血液検査データは、総リンパ球(TLC)、血清総タンパク(TP)、アルブミン(Alb)、総コレステロール(TC)などがあります。
また、誤嚥性肺炎の疑いがある患者の場合には、C-リアクティブプロテイン(CRP)、白血球数(WBC)を確認することも大切です。
これらは炎症の指標なので、数値が高い場合には誤嚥性肺炎の疑いが高まります。

つい忘れがちな食形態の確認
現在の食形態を問診したら、必ず実際の食形態を確認することをお勧めします。
なぜなら、ペースト食、刻み食などと言っても、人によっては、その内容が大きく違うことがあるためです。
例えば、同じ「極刻み食」と言っても、施設によって写真のように大きく違います。

施設の場合、どちらかと言えば安全側に柔らかい食事になりがちですし、退院した時の食形態のままということもよくあります。
患者の機能に合わせた食形態が提案できれば、歯科医院に対する信頼度・期待度が向上するでしょう。
患者の声の確認も忘れずに
話す器官は咀嚼器官とイコールなので、舌、頬、口唇などを使って発せられた声を聞くことで、咀嚼機能に関わる口腔機能の診断に利用することができます。
湿性嗄声があれば、唾液の咽頭残留や喉頭周囲の残留が疑われ、咽頭期障害の可能性があることはよく知られています。
一方、ハスキーボイスみたいなかすれたような声である気息性嗄声は、声帯の閉鎖が甘くなって呼吸が漏れてしまうことが原因で起こる声です。
気息性嗄声があると、声帯結節や声帯ポリープ、反回神経麻痺などの可能性が疑われます。

施設の場合、どちらかと言えば安全側に柔らかい食事になりがちですし、退院した時の食形態のままということもよくあります。
患者の機能に合わせた食形態が提案できれば、歯科医院に対する信頼度・期待度が向上するでしょう。
これらは、摂食嚥下障害の問診で漏れがちな事項のほんの一部です。
問診で患者の状態を詳しく知ることができれば、摂食嚥下障害対応に役立つことは明白です。
今一度、摂食嚥下診療の問診と診察の総復習をすることをお勧めします。
このDVDを観ることで得られることは…
- 訪問診療に特徴的な問診のポイントがわかるので、診療に役立ちます
- 身体所見の取り方や口腔機能測定の潜入動画があるので、今日からの診療に活用できます
- 患者の声からわかる咀嚼機能、咽頭残留および声帯閉鎖不全の可能性
- 口腔内所見のポイントと注意すべき点がわかるので、正しい診断に役立ちます
- 摂食嚥下障害患者の食形態で注意すべきこと
などとなっています。
このDVDの収録内容をご紹介すると…
Part1:講義
問診の取り方
- 問診で確認すること
- 主訴
- 身長体重
- 訪問診療での病歴の特徴
- 脳血管障害
- 脳卒中患者と嚥下障害
- 誤嚥性肺炎
- 誤嚥性肺炎の診断基準
- 常用薬
- 栄養状態
- 血液検査
- 現在の食形態
- 経口摂取していない患者の場合は?
口腔内所見の取り方
- 患者の声からわかること
- 頬の評価
- 口唇の評価
- 舌の評価
- 軟口蓋の評価
- 補綴物の状態
- 口腔衛生状態
- 口腔アセスメントツール OHAT(Oral Assessment Tool)の活用
- 習熟度テスト(Part1)
Part2:潜入動画
身体所見の取り方
- 身体所見のポイント
- バイタルサイン
- 脱水の疑いがあるときは
- 認知レベル
- Myerson兆候
- 下腿周囲長
- 手回内回・外試験
- 鼻−指−鼻外試験
- 上肢の挙上
- 上肢の筋緊張
口腔機能の測定
- 口腔機能低下症の診断基準
- 口腔衛生状態(視診)舌苔の付着程度
- 口腔乾燥(口腔粘膜湿潤度)
- 咬合力検査
- 舌口唇運動機能低下
- 低舌圧
- 咀嚼能力
- 嚥下機能
嚥下機能のスクリーニング
- 改訂水飲みテスト(MWST)
- 食物テスト(FT)
- 習熟度テスト(Part2)
- 摂食嚥下診療の問診と診察まとめ
などなど。
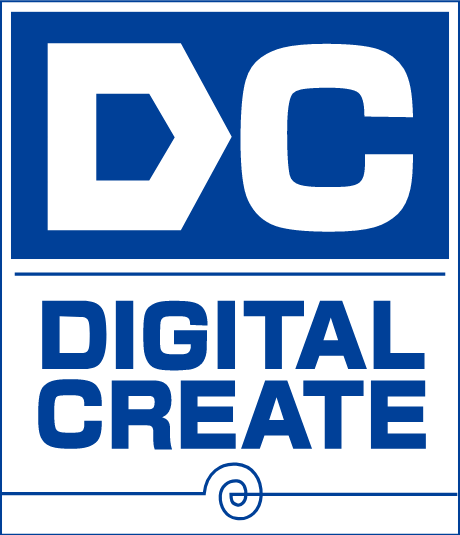

M.Y. –
摂食・嚥下の問診と診察のやり方がわかり易く説明されていた事がとても良かった
T.K. –
誤嚥性肺炎のチェック項目について詳しく学べました。マイヤーソン兆候は、参考になりました
S.I. –
患者さんの声からわかることの項目が特に目からウロコでした。今後に活かしたいと思いました
R.M. –
高齢者中心の摂食嚥下障害の問診と診察時の注意の総復習となりました
Y.M. –
口腔機能低下症の診断を行うための検査を今すぐできるものから取り入れていきたいと思います