訪問先で、どこを診たら良いのか悩んだことはありませんか?
要介護高齢者の全身状態は日々変化します。調子の良い時もあれば、悪い時もあります。調子が良さそうに見えても、診療の最中に急変する可能性もあります。
バイタルサインを確認することは重要ですが、それだけで良いのでしょうか?
日本大学 歯学部の米永先生は「全身を診ることが大事」とおっしゃいます。
顔の表情を診てから目、鼻、口の順に診る
 顔から順番に診ていきます。まず顔の表情を診てから、目、鼻、口と診ていきます。次に咽頭部分。もちろん喉も外からも中も診ていきます。
顔から順番に診ていきます。まず顔の表情を診てから、目、鼻、口と診ていきます。次に咽頭部分。もちろん喉も外からも中も診ていきます。
四肢を診ることも大事
 寝た状態の患者の場合には四肢を診ることが大事。特に、訪問診療では足のむくみを診ることが重要です。血流の循環状態が足にはっきりと現れるためです。
寝た状態の患者の場合には四肢を診ることが大事。特に、訪問診療では足のむくみを診ることが重要です。血流の循環状態が足にはっきりと現れるためです。
手の湿潤・乾燥状態や爪の状態を診る
 「手当て」という言葉もあるように、手の状態を診ることも大切です。湿潤しているか、乾燥していないかを確認します。
「手当て」という言葉もあるように、手の状態を診ることも大切です。湿潤しているか、乾燥していないかを確認します。
また、爪の状態を見れば貧血の他、心不全や呼吸不全の可能性があるかどうか、あるいは免疫機能が落ちていないかといったことがわかります。
患者さんの全身を診ることで、さまざまな情報を得ることができます。
上記以外にも、便秘や頻尿になっていて食べられない原因や嚥下機能が低下しているサインなども確認できます。
また、服薬剤から得られる情報もたくさんあります。
このようなことを知っていれば、安全な訪問診療に役立つだけでなく、患者さんに最適なケアができるようになります。
このDVDを観ることで得られることは…
- 安全な歯科診療に必須の基本的な考え方と知識が身につきます
- 患者の全身状況を把握するために診るべきポイント
- 緊急時の具体的な対応方法と準備しておくべきものとは?
- 嚥下障害ではない高齢患者が食べられない意外な理由と解決方法
- 医科歯科連携に必要な基準・ガイダンス・用語
などとなっています。
このDVDの収録内容をご紹介すると…
Part1:講義
1. 訪問歯科診療における全身管理の重要性
- 超高齢社会に対応した医学的歯学を実践する
2. 診療前の全身状態評価のポイント(バイタルサイン測定、問診)
- 歯科医師の救命救急研修ガイドライン
- 診察
- 体温
- 呼吸
- 脈拍
- 血圧
- 気道確保
- エアウエイの挿入
- 呼吸管理
- BVM(バッグ・バルブ・マスク)による用手人工呼吸
- 循環保護
- 経胸壁用手心臓マッサージ
- AEDによる除細動(VF/脈無しVT)
- モニター等
- 非侵襲的モニターの装着及び検査
- 薬物/輸液等
- ACLSのVF/VT、PEA 心静止のアルゴリズムで使用する薬剤の使用
- その他
- 病歴や現症の聴取
- チームカンファレンスへの参加
3. 訪問診療時の急変対応(意識障害、血圧低下など)
- 意識障害
- 重症度の把握:ショック指数
- アスピリン喘息
- アナフィラキシーショック
- 心電図のPoint
- 酸素濃度低下の人体への影響(ヘンダーソンの分類)
- 参考:救急対応のための必需品(歯科備品)
- 救急患者を診る際の最も重要なこと
4.認知症患者や高齢者の特徴と対応方法
- 認知症患者や高齢者の特徴
- ユマニチュードの実践
- 要支援・要介護認定
5.医科からの情報をどう活用するか(診療情報提供書の読み方)
- 栄養指標と呼ばれる検査項目を読めるようになろう
- 血清蛋白質①
- 血清蛋白質②
- 血清脂質
- 免疫能の指標
6.訪問診療のリスク管理(誤嚥性肺炎、GLIM低栄養など)
- 誤嚥性肺炎のABCDEアプローチ
- 誤嚥性肺臓炎と誤嚥性肺炎の違い
- 誤嚥性肺炎の投薬
- GLIM基準(Global Leadership Initiative on Malnutrition)
- 簡易栄養状態 評価表(MNA)
- 栄養管理のコツ
- エネルギーの産生経路
- まとめ(振返りのポイント)
- 復習テスト
Part2:潜入動画編
- 医科の訪問診療の流れを追うー出発前―
- 症例①
- 訪問診療現場でのバイタルサイン測定の実践
- 症例②
- 診療情報提供書をもとに治療計画を立てる場面
- 患者の全身状態を確認しながら診療する様子
- 症例③
- 緊急時の対応シミュレーション(意識低下時の対応)
- 医科の訪問診療の流れを追う-帰院後-
- 症例④
- ジギタリス中毒について
- 症例⑤
- パーキンソン病について
- 症例⑥
- 便秘について
- 血圧測定
- 食欲がないんです…
- パーキンソン病概要
- 呼吸
- 各薬剤の作用機序からみたポジショニング
- まとめ(振返りのポイント)
- 復習テスト
などなど。
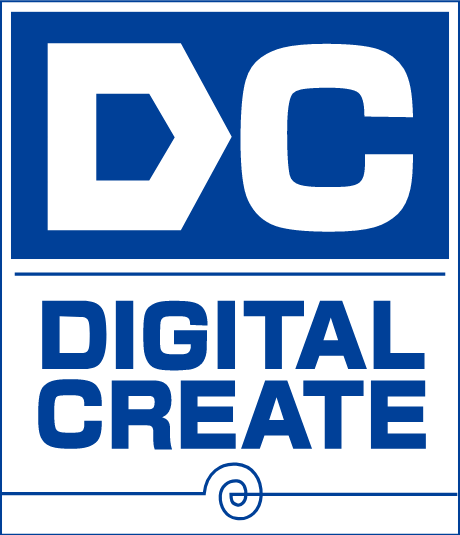
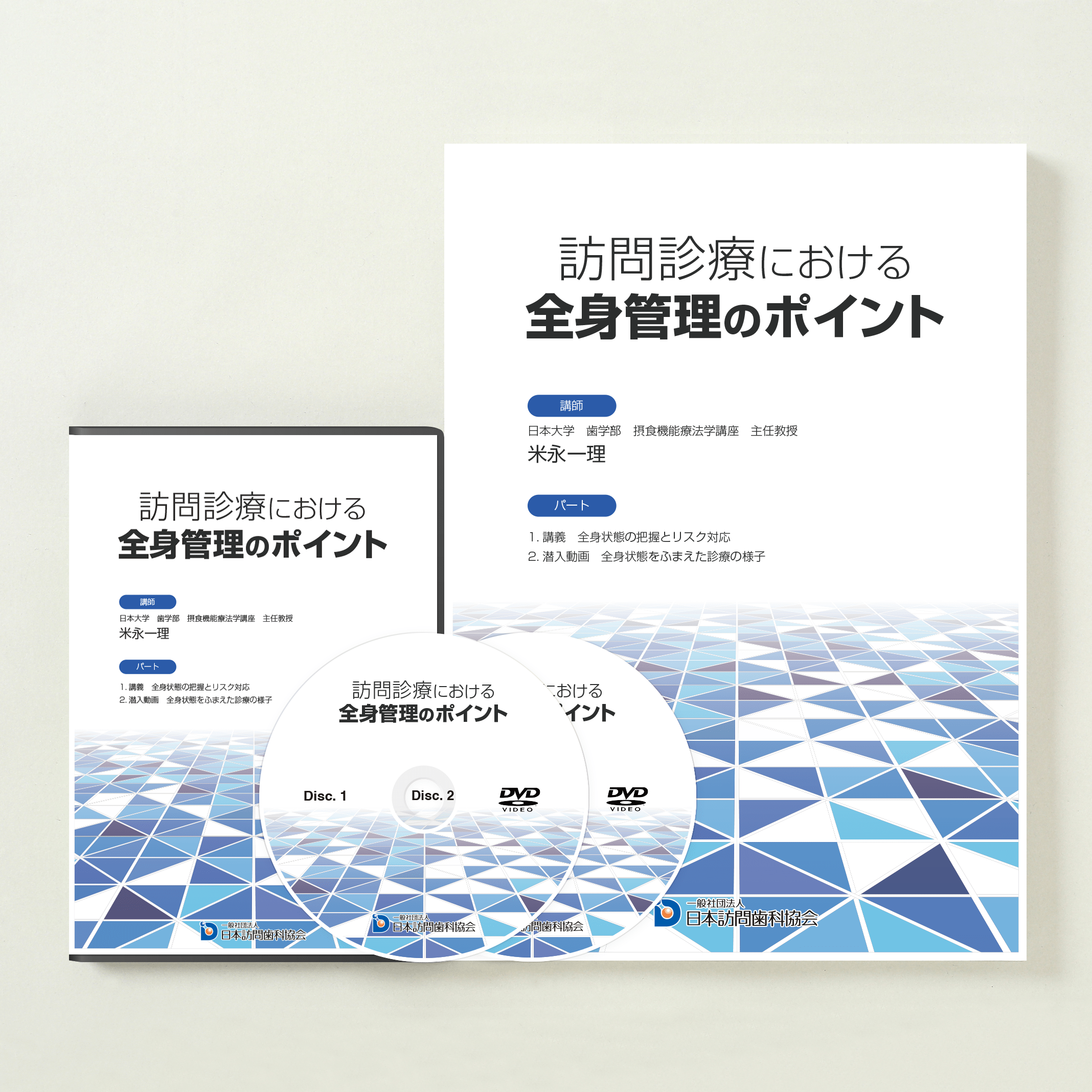
M.S. –
潜入動画を踏まえての説明が非常にわかりやすかったです
S.I. –
患者様にお会いして最初の観察するポイントについてが印象的でした
R.M. –
臨床の場でも手の爪をみたりはしていましたが、確かに3つの部分の清潔は大切だと再認識です。また舌の挙上ができるか否かは気にしていましたが、前方への挺出不良の患者さんへの聞き取りの仕方も一層気を付けていきたいと思いました
K.Y. –
食べられないという症状に対し、すぐに嚥下機能訓練を思い浮かべてしまいますが、なぜ食べられないのかをまず診断すること大切であることを知らされました。ジギタリス中毒が原因であることが判明すれば、薬の変更を指示することによって食事ができるようになる事例も示していただきました。また、パーキンソン病の薬剤が影響している場合には、薬剤調整することで解決できることもわかりました
M.H. –
パーキンソン病で投薬内容で摂食出来る事、四肢を観察する事が勉強になった