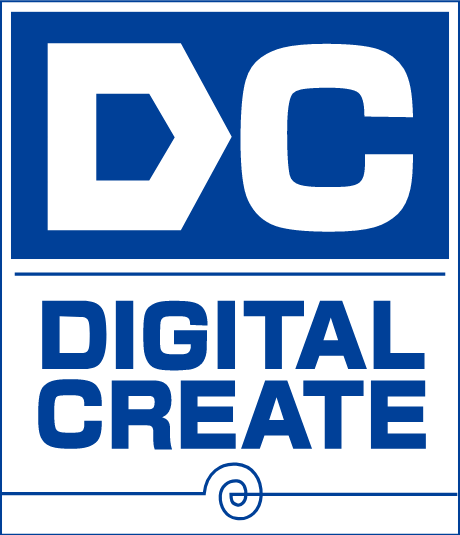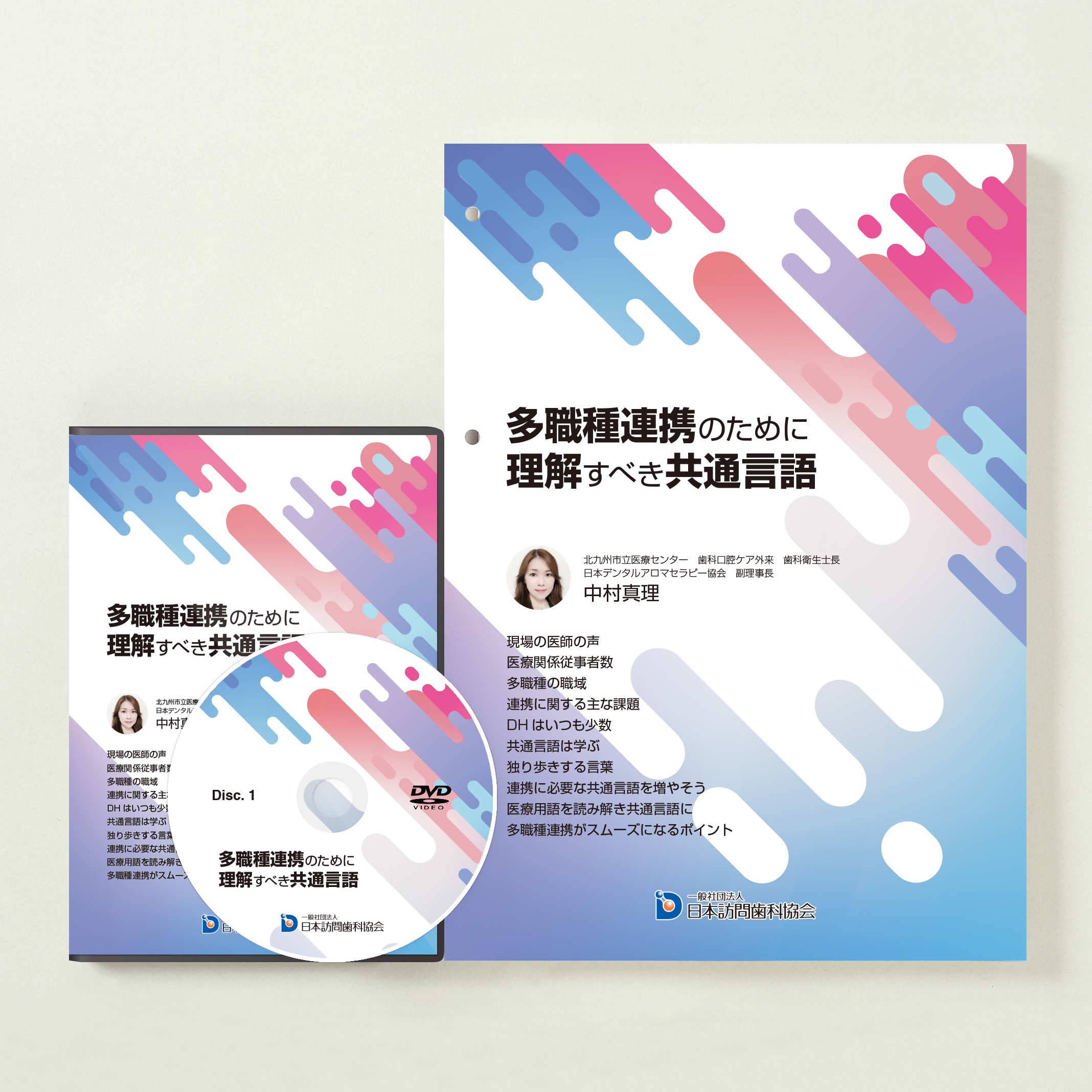このDVDの収録内容の一部をご紹介すると…
- 多職種協働における目標
- 多職種連携のイメージ
- 現場の医師の声
- 医療関係従事者数
- 多職種の職域
- 「連携」について規定がある法律とその条文(抄)
- 「他の医療関係者との連携」について規定がある法律とその条文(抄)
- 病院や介護施設等で業務に従事する歯科衛生士について(通知)
- 歯科衛生士に対する主治の歯科医師または医師の指示
- 連携に関する主な課題(例)
- 歯科のある病院・歯科のない病院 歯科衛生士単独の現場
- 地域歯科医師会・病院との連携/訪問歯科・病院スタッフとの連携
- 口腔機能、口腔環境の情報を共有
- NSTラウンド・症例検討
- 共通言語は学ぶ
- 日本歯科医学会 医科歯科連携に必要なキーワードリストより
- 多職種連携、協働のポイント
- 独り歩きする言葉
- 専門職への理解を深める
- 看護・介護の実践
- 看護記録より
- 多職種協働の実際
- 連携に必要な共通言語を増やそう
- 施設での情報共有⇒共通言語に
- 多職種連携ノートに記載
- 多職種連携ノートから・共通言語
- 医療用語を読み解き共通言語に
- バイタルサイン編
- 身体・機能編
- 採血・血算・生化学検査
- 治療・疾患関連
- 同音異義語
- 漢方薬編(ツムラ)
- 多職種連携がスムーズになるポイント
- 口腔癌術後 口腔ケアは?食事は?
- 舌半切再建
- 口腔癌術後の在宅ケアはどうしたらいい?
- 皮弁再建術後
- 舌接触補助床(PAP)
- STと情報共有
- まとめ
などなど。
このDVDを観ることで得られることは…
- 多職種連携に関する主な課題が事前にわかるので、スムーズな連携を実施できるようになります
- 多職種連携の際に陥りがちな落とし穴。これを念頭に置かないと患者さんのケアが十分にできなくなります
- チーム医療が機能するために決定的に重要なこと
- 当たり前だが、実行が難しい心構え。訪問のたびに確認すると、多職種と良好な関係を築くことができるようになります
- 他職種の理解を深めるために知っておきたい法律と条文
- 他職種から誤解を受けにくくするためのちょっとした言い方
- 医科歯科連携に必要なキーワードリスト。学ぶべき用語が簡単に把握できます
- 他職種に歯科を理解してもらうための方法
- これは知っておくべき医療用語。これを知らないと、他職種から医療者として認められなくなる恐れがあります
- 多職種連携を成功させるためのツールとは?
- 多職種と意思疎通が困難になる同音異義語がわかります
- 多職種連携がスムーズになる5つのポイント
- 多職種連携の実例があるので、多職種連携の模擬体験ができます
などとなっています。