このDVDの収録内容をご紹介すると…
第1部:今さら聞けない在宅療養支援制度
- 緒言
- チームで進める浸透のための3段階
- 地域情報づくりが、地域医療づくりとなる
- 超高齢社会に求められる医療像
- アドバンス・ケア・プラニング
- 行動を起こすきっかけは何か?
- 継続しなければ効果は出ない
- 健康行動を継続させるために
- ナッジを利用した環境整備
- 在宅療養で利用できる制度
- 在宅療養サポートメンバー
- シームレスな曜日毎の多職種介入の例
- 医療か介護か
- 訪問看護のルール
- 介護給付(介護保険サービス)
- 介護施設
- 要支援・要介護認定
- 主治医意見書の役割
- 意見書の書き方
- 介護が必要となった主な原因
- 認知症施策推進大綱
- 認知症の中核症状と周辺症状
- うつ病と認知症の関係
- うつ病とアルツハイマー型認知症の臨床的特徴
- せん妄と認知症の臨床的特徴
- せん妄の原因と影響を及ぼす主な薬剤
- 予防可能な認知症危険因子の寄与
- 認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)の概要
- 認知症初期集中支援チーム
- 地域包括ケアシステムのための認知症アセスメント
- 認知症高齢者ケアの基本
- 認知症のリハビリテーション
- 成年後見制度
- 成年後見制度の背景
- 成年後見制度の仕組み
- 成年後見制度の利用概況
- 成年後見制度の特徴
- 日常生活自立支援事業
- 高齢者虐待
- 在宅医療の費用
- 診療項目ごとの料金
- 最も自己負担が掛かるのは?
- 要介護1 78歳 糖尿病・うつ病
- 要介護2 70歳 肺腺癌末期
- 要介護5 85歳 認知症
- 最後に
第2部:疾患別対応法 〜こんなときどうする〜
- 内科医の診断治療の考え方
- 意識障害
- 高血圧症
- 血圧区分の分類
- 糖尿病
- 糖尿病概要
- 糖尿病連携手帳
- テスターの使い方
- 血糖測定器
- 心房細動
- 心房細動治療(薬物)ガイドライン2013年改訂版
- 狭心症
- 狭心症の分類
- 心不全
- 心不全概要
- 弁膜症
- 脳梗塞
- 脳梗塞概要
- 脳出血
- どれが出血でしょうか
- 喘息
- 喘息予防・管理ガイドライン2018
- アスピリン喘息
- アスピリン喘息対応時の注意点
- 判明していること
- NSAIDs過敏喘息における安全な点滴静注用ステロイドの使用方法
- アナフィラキシーショック
- アナフィラキシーショックへの対応
- 妊婦・授乳中
- 妊婦・授乳中でわかっていること
- 局所麻酔アレルギー
- パニック障害
- 半夏瀉心湯
- 甲状腺機能亢進症
- ステロイド内服
- 腎不全
- 慢性腎不全概要
- 腎機能低下時の主な薬剤投与量一覧
- 人工透析
- 救急患者を診る際の最も重要なこと
- 地域包括ケア病棟協会
- ポイント
第3部:歯科医師による救急救命処置 〜どこまで何をやれるか〜
- 歯科医師による救急救命処置で認められていること
- 歯科医師による救急救命処置で認められていないこと
- 歯科医師の救命救急研修ガイドライン
- 趣旨 抜粋
- 二次救命処置研修
- 研修水準A~Dのカテゴリー分類
- 学習項目
- 診察
- バイタルサインのチェック
- 意識レベル:JCS、GCS
- 体温
- 呼吸
- 冷汗で何を疑うか
- 重症度の把握:ショック指数
- ショック時の対応
- 脈拍
- 血圧
- 血圧測定
- 頭頸部の視診、触診
- 胸部の視診、触診、聴診、打診
- 四肢の視診、触診
- 打腱器などを用いた神経学的診察
- 気道確保
- 用手気道確保
- 経口エアウエイの挿入
- 経鼻エアウエイの挿入
- 参考:胃管交換
- 参考:胃婁交換
- 呼吸管理
- BVM(バッグ・バルブ・マスク)による用手人工呼吸
- 麻酔器、マスクによる用手人工呼吸
- 気管挿管下の用手人工呼吸
- 循環保護
- 経胸壁用手心臓マッサージ
- AEDによる除細動(VF/脈無しVT)
- 末梢静脈路確保
- モニター等
- 非侵襲的モニターの装着及び検査
- 静脈採血
- 静脈採血:末梢神経障害に注意
- 大腿静脈採血
- 動脈採血
- 薬物/輸液等
- ACLSのVF/VT、PEA、心静止のアルゴリズムで使用する薬剤の使用
- 救命救急センター、救急部における救急輸液の実施
- その他
- 創洗浄、創縫合(歯科口腔外科領域のもの)
- 病歴や現症の聴取
- チームカンファレンスへの参加
- 栄養指標と呼ばれる検査項目
- 血清蛋白質
- 血清脂質
- 免疫能の指標
- ちょっと未来の話 イートロス医学
- まとめ
などとなっています。
このDVDを観ることで得られることは…
- 高齢有病者の訪問診療を安全に行うために必要な在宅療養制度の概要と有病者への対応方法や歯科医師による救急救命の知識が身につきます
- 多職種とのスムーズな連携に欠かせない知識がまとまっているので、安心・安全な歯科治療に役立ちます
- 医療保険か介護保険のどちらが適用されるかを簡単に判断する方法
- 意外と知らない10の訪問看護ルール。これを知っていると訪問看護師と連携を取りやすくなり、安心・安全な歯科治療を提供できるようになります
- 医療と介護の連携のための最も基本的なツールである「主治医意見書」。ケアプラン作成の情報源にもなっているので、どんな内容が書かれているのかを知っていれば、歯科診療の際に役立ちます
- 予防可能な認知症危険因子とは?早期に認知症に気づいて安全な歯科治療に寄与できる可能性が高まります
- 認知症患者への多職種連携に役立つ「地域包括ケアシステムのための認知症アセスメント」の概要
- 高齢者、障害者が自らの意思で、契約に基づき介護・福祉サービスを利用できるようにするための「成年後見制度」の概要が理解できるようになります
- 要介護高齢者の合併症・偶発症を防ぐために治療前に確認しておくべきこと
- 糖尿病患者が使用している血糖値測定器具の使い方。これを知っていれば意識障害が発生した時などに速やかに血糖値を測定することができるので、正しい対処ができるようになります
- 処方薬を確認するだけで、心不全の症状やリスクステージを把握できるようになります
- 喘息患者の症状がコントロールできているかどうかを判断する方法
- 歯科医師の二次救命処置で求められる内容が把握できます
- ショック時にとるべき体位とは?誤った体位の場合、嘔吐誘発や呼吸運動障害が起こる可能性があります
- 爪の形状を見ただけで、肺や心臓に疾患の疑いがある患者、鉄欠乏性貧血の疑いのある患者を見つけることができるようになります
- 様々な気道確保のやり方や用手人工呼吸方法が把握できます
などなどです。
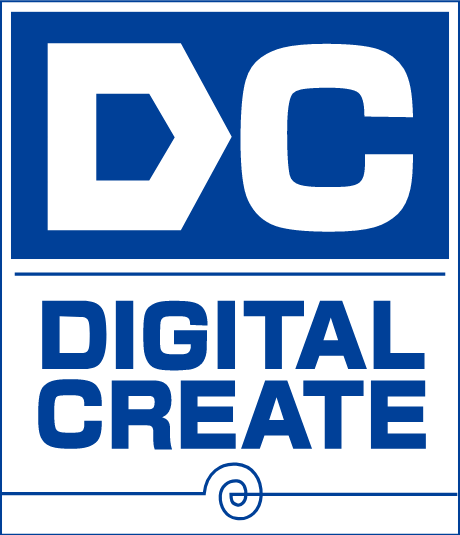
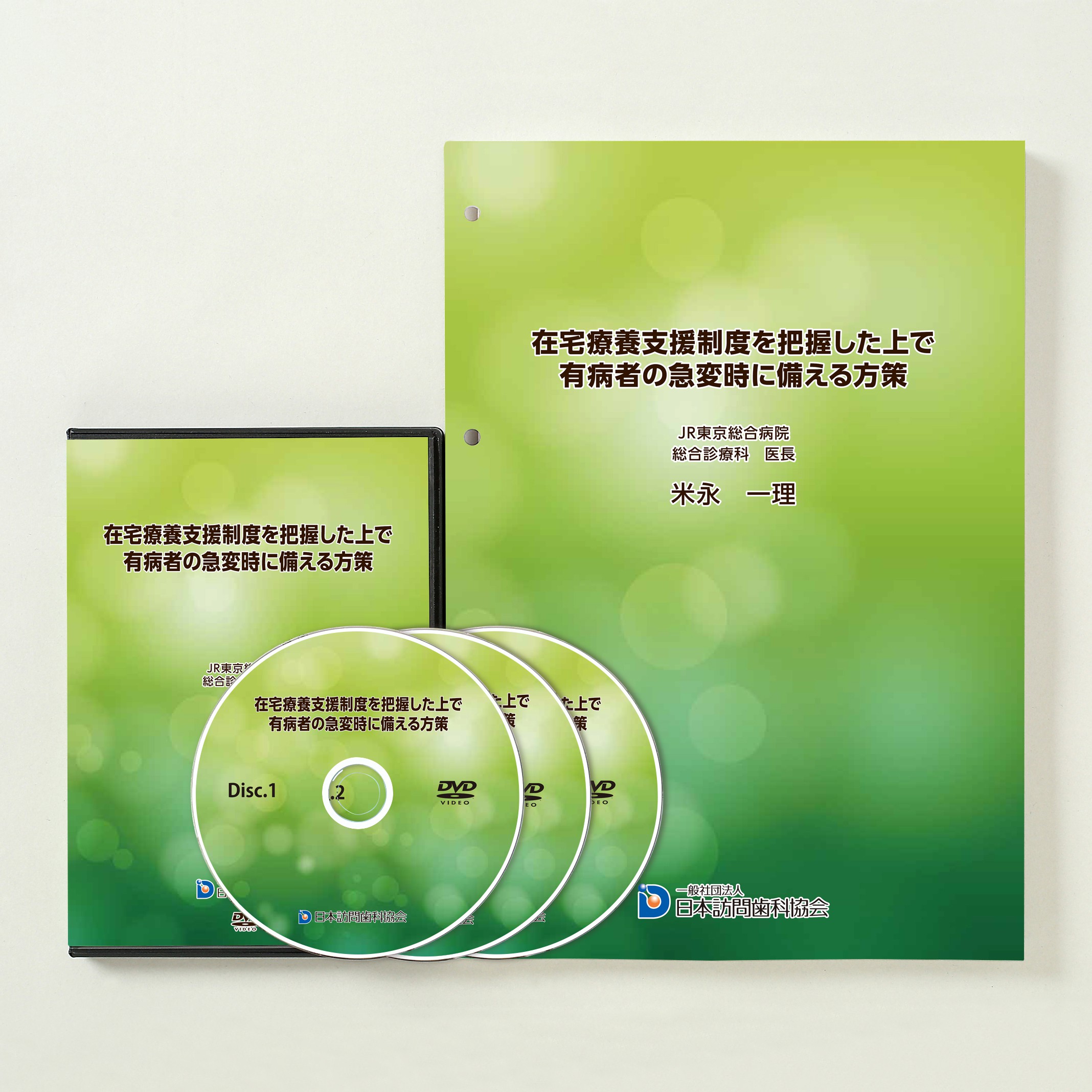
A.F. –
面白かった
A.K. –
全体的に良かった。
T.M. –
ほとんど聞いたことがない話ばかりだったので、とても参考になりました。
M.Y. –
非常にためになりました。
K.U. –
難しい内容でしたが、面白くお話しいただいたので、もっと勉強したいと思いました。
M.S. –
聞きやすいので全部がためになりました。
N.K. –
内容が少し難しい印象でしたが、とても勉強になりました。
N.K. –
救急処置について学ぶことが良かった。
K.F. –
他の文献からそのままコピーではなく、先生の知見を元に改変してあり、とてもよかった。
G.N. –
疾患別対応法について詳しく知れてよかったです。
K.T. –
なかなか馴染めない内容で難解でしたが、今後、理解に努めていきたい。
S.F. –
実際の動画での使用方法が役に立ちました。
Y.K. –
救急患者を診る際に最も重要なこと;病態を正確に評価し、標準化された手順で、適切な蘇生処置を施行する。定期的な訓練を行う。リアルタイムで記録を記載すること。
S.H. –
医科での基礎検査の部分、とくに栄養状態での血液検査の値など非常に興味深いものがありました。
K.H. –
胃瘻の患者さんは診ているが、内科的視点ではみていなかったので勉強になりました。
T.T. –
緊急時の対応については、わかっているつもりでも繰り返し復習して、常々意識を高めておく必要があると感じました。
M.Y. –
訪問歯科医師も内科的疾患に罹り全身状態の悪い患者さんを診る事が多くなった。米永先生の内科的病気についてのわかり易い解説が良かった。
M.O. –
難しかった。1回では理解できない内容であった。
E.I. –
「ときどき入院、ほぼ在宅」が心に残りました。
R.M. –
知っているようであやふやだった訪問看護のルールがよくわかりました。救急救命処置については、救急救命士に的確に伝えられるだけの力ぐらいは持てるために復習していきます。糖尿病連携手帳に記載をしていけるようスタッフと連携していきたいと思います。
A.H. –
知っている内容に関しては復習できた。また知らない内容もあり勉強になりました。